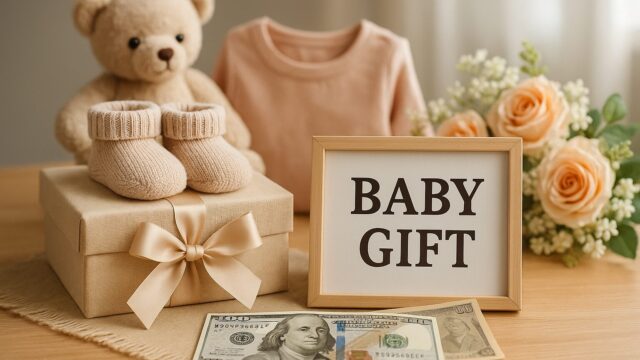内祝いを郵送する機会は、出産や結婚、新築、快気祝いなど、人生の節目ごとに訪れます。しかし、直接会って渡せない分、郵送では「本当に気持ちが伝わっているかな?」と不安になることも。そんなときに大切なのが、贈り物と一緒に添えるメッセージです。この記事では、内祝いを郵送するときのマナーから、シーン別・相手別に使える例文、そして心を込めて文章を書くためのコツまで、すぐに使える情報をたっぷりご紹介します。これを読めば、郵送でもしっかりと感謝の気持ちを届けられるはずです。
内祝いを郵送する時に押さえておきたい基本マナー
内祝いを郵送するシーンとは?
内祝いを郵送する場面は、現代では非常に多くなっています。特に相手が遠方に住んでいて直接会えない場合や、相手が多忙で訪問の時間を取ってもらうことが難しい場合に選ばれます。例えば、出産祝いをくれた友人が他県や海外に住んでいる場合、結婚式に参列できなかった親戚からお祝いをいただいた場合、新築内祝いで遠方の知人にお礼をする場合などが典型です。郵送のメリットは、相手の都合に合わせやすいことです。訪問だと在宅時間を合わせる必要がありますが、宅配便や郵便であれば時間指定や再配達も可能で、相手に負担をかけずに済みます。特に出産直後や病気療養中など、訪問が体力的・精神的に負担となるタイミングでは、郵送が思いやりのある選択となります。ただし、郵送は手渡しのように直接感謝を伝えられないため、贈り物だけが届くと事務的な印象になってしまう恐れがあります。そこで重要になるのが、同封する手紙やメッセージカードです。短くても構わないので、感謝の言葉と相手を気遣う一文を添えることで、気持ちがぐっと伝わります。また、送るタイミングにも配慮が必要です。内祝いはお祝いをいただいてから1か月以内が基本マナー。出産内祝いならお宮参り(生後1か月頃)に合わせるのが一般的です。早すぎると「用意していたのでは?」と思われ、遅すぎると感謝の気持ちが薄れたように感じられるため、3日〜1週間程度間をあけるのが理想です。郵送は便利ですが、細やかな心配りを欠くと味気ない印象になってしまいます。相手を思う気持ちを、梱包や文面にも込めることが大切です。
郵送にする場合の注意点
郵送での内祝いは、相手の手元に届くまでを想定した入念な準備が求められます。まず破損防止が第一です。陶器やガラス製品はもちろん、瓶や缶詰も衝撃で破損や変形が起きることがあるため、緩衝材でしっかり包みます。食品なら賞味期限や保存状態の確認も必須です。特に生鮮品や冷蔵・冷凍品は、受け取りが遅れると品質が損なわれるため、事前に相手の都合を聞き、確実に受け取れる日を指定して発送しましょう。配送伝票には「ワレモノ」「天地無用」「冷蔵」などの注意書きを明記し、できれば宅配業者にも口頭で伝えると安心です。また、送り状の品名欄には「食品」「ギフト」など簡潔な表記を心がけ、中身が詳細にわかりすぎないようにします。値札や領収書は必ず外し、金額がわかるものは同梱しないのがマナーです。配送方法は品物に応じて選びましょう。重く大きい物や壊れやすい物は宅配便、小さく軽い物や商品券、カタログギフトなどは書留やレターパックが適しています。いずれの場合も追跡可能なサービスを利用すれば、配送トラブル時の対応がスムーズです。郵送は顔を合わせないからこそ、細部の気配りが「丁寧さ」として相手に伝わります。
包装・熨斗の正しい選び方
内祝いでは、包装と熨斗(のし)の選び方が非常に重要です。熨斗はお祝いの種類によって結び方を使い分けます。出産・新築・進学などの「何度あっても良いお祝い」には紅白の蝶結びを、結婚や快気祝いなど「一度きりが望ましいお祝い」には紅白の結び切りを選びます。表書きは出産・結婚・新築などの場合「内祝」、快気祝いの場合は「快気内祝」とし、下段に贈り主の姓またはフルネームを記します。郵送の場合は贈り物を包装紙で包み、その上に熨斗紙をかける「外のし」が一般的です。さらに配送用の箱に入れ、緩衝材で保護することで見栄えと安全性を確保できます。デパートやギフトショップでは、郵送に適した二重包装サービスを用意している場合が多く、依頼すれば仕上がりもきれいで安心です。熨斗は形式だけでなく「贈る側の心」を形に表す役割があり、受け取ったときの印象を大きく左右します。正しい選び方と丁寧な扱いが大切です。
宅配便・郵便の使い分け
配送方法は贈る品物や相手の状況に合わせて選びます。重く壊れやすい物や冷蔵・冷凍が必要な食品は宅配便が適しています。大手宅配業者では時間帯指定やクール便などのオプションが充実しており、安全に届けられます。一方、小さく軽い物や商品券、カタログギフト、手紙などは郵便も有効です。郵便局の「ゆうパック」は日時指定や追跡が可能で、贈答品向けの取り扱いにも対応しています。また、相手が日中不在が多い場合は、コンビニ受け取りや宅配ボックスへの配達を指定できるサービスも便利です。事前に相手の受け取りやすい方法を確認し、最適な手段を選ぶことが、スムーズな受け渡しと好印象につながります。
相手に喜ばれるタイミングとは?
内祝いを送るタイミングは、受け取る側の印象を大きく左右します。お祝いをいただいてすぐに返すと用意していたように見え、逆に遅すぎると感謝の気持ちが薄れているように感じられることがあります。一般的には、3日〜1週間程度間をあけ、遅くとも1か月以内に送るのが理想です。出産内祝いならお宮参りに合わせて、生後1か月前後、結婚内祝いは式後1か月以内、新築内祝いは引っ越し後1〜2か月以内が目安です。また、相手の生活や季節行事に合わせた配送日を選ぶと、より気遣いが感じられます。例えば、暑中見舞いや年末の挨拶を兼ねて送れば、季節感が出て印象も良くなります。タイミングは単なる日程調整ではなく、相手を思いやる心を表す要素です。
メッセージを添える意味と効果
なぜメッセージカードが大切なのか
内祝いを郵送する際、贈り物と一緒にメッセージカードを添えることは、単なる形式ではなく、感謝の気持ちを相手に確実に届けるための大切な要素です。郵送は便利ですが、手渡しのように直接表情や声で想いを伝えることができません。そのため、贈り物だけを受け取った相手は「ありがとう」という気持ちが本当に込められているのか、少し事務的に感じてしまう場合もあります。そこで、手書きの一言でも構いませんので、メッセージカードを添えることで「あなたのために準備しました」という気持ちをしっかりと表現できます。また、メッセージは贈り物の価値を引き立てる効果もあります。例えば「先日は素敵なお祝いをありがとうございました。家族みんなで喜んでおります。」という一文があるだけで、品物が単なる物ではなく、感謝の象徴として受け取られます。さらに、カードは贈り物を開ける前に目に入るため、最初の印象を決定づける存在でもあります。郵送時にはメッセージカードをギフトと同じ箱に入れる方法と、別封筒で送る方法がありますが、ギフトの中に入れる方が開封時に自然な流れになります。手書きに自信がなくても、パソコンや印刷サービスを使って整った文字にすることは可能です。ただし、完全に印刷だけではなく、最後に一言でも手書きで添えると温かみが増します。このひと手間が、相手の心に残る内祝いを作り上げる鍵となります。
手紙とカードの使い分け
内祝いに添える文章は、長さや形式によって「手紙」と「カード」を使い分けるのが理想です。カードは簡潔で短いメッセージを伝えるのに向いており、例えば職場の同僚や友人、カジュアルな関係の相手に適しています。可愛らしいデザインや華やかな柄のカードは、特に出産内祝いなどで喜ばれる傾向があります。一方、手紙は文章量が多く、丁寧な挨拶や近況報告まで含めたい場合に最適です。例えば、結婚内祝いでお世話になった上司や年配の親戚など、格式や礼儀を重んじる相手には手紙がふさわしいでしょう。手紙では冒頭の挨拶文(時候の挨拶や安否伺い)、本題(お礼の言葉と贈り物の説明)、結び(健康や幸福を祈る言葉)という流れを意識すると、読みやすく好印象です。また、郵送の場合は手紙やカードの紙質にも気を配ると良いでしょう。高級感のある厚手の紙や封筒を使えば、開封した瞬間に特別感を演出できます。カードと手紙の使い分けは、相手との関係性と贈る場面によって柔軟に判断することが大切です。
メッセージが好印象を与える理由
メッセージは、相手に「自分のために時間を割いてくれた」と感じてもらえるからこそ、好印象を与えます。現代では、オンラインショッピングやカタログギフトのように、手軽に贈り物を送れるサービスが増えています。その一方で、そこに手書きのメッセージが添えられていると、格段に特別感が増します。これは心理学的にも「パーソナルタッチ効果」と呼ばれ、相手の名前や具体的なエピソードが含まれると、贈り物がより心に残るとされています。また、文章を通して「自分がどれだけ感謝しているか」を直接表現できるため、贈り物の金額や内容以上の価値を生み出せます。さらに、メッセージは相手との関係性を深めるきっかけにもなります。「またお会いできる日を楽しみにしています」などの前向きな言葉を添えることで、今後の交流につながることもあります。このように、メッセージは単なる添え物ではなく、内祝い全体の印象を左右する大きな要素なのです。
メッセージなしだとどう思われる?
もし内祝いを郵送する際にメッセージを添えなかったら、相手はどう感じるでしょうか。もちろん、多くの人は贈り物そのものに感謝しますが、中には「少し味気ない」「事務的に感じる」と思う人もいます。特に、普段から親しいやりとりをしている相手や、大きなお祝いをしてくれた相手に対しては、言葉で感謝を伝えないことが失礼と感じられる場合があります。また、内祝いの意味は「いただいたお祝いへの感謝の気持ちを形にすること」です。そこに言葉がないと、相手は「本当に感謝してくれているのかな?」と不安に思うかもしれません。さらに、郵送では渡す場面の笑顔や会話がないため、印象を補うのは文章しかありません。贈り物がどれだけ豪華でも、メッセージがないと印象は半減してしまうことを覚えておきましょう。
文字数や文体の基本マナー
内祝いに添えるメッセージの文字数は、短すぎず長すぎないことが大切です。目安としてはカードなら50〜100文字程度、手紙なら200〜400文字程度が適切です。短すぎると事務的に感じられ、長すぎると読むのが負担になってしまいます。文体は、相手との関係性によって使い分けます。上司や年配の方には敬語をきちんと使い、友人や同僚には少し砕けた柔らかい言葉でも構いません。ただし、どんな相手でも丁寧な言葉遣いを心がけ、「拝啓」「敬具」などの形式を守ると安心です。また、句読点の位置や改行にも気を配ることで、読みやすく整った印象を与えられます。最後には必ず相手の健康や幸せを祈る一文を添え、気持ちよく読み終えてもらえる文章を意識しましょう。
内祝いの郵送に使える定番メッセージ例文
出産内祝いで使える例文
出産内祝いのメッセージは、新しい家族が増えた喜びと、いただいたお祝いへの感謝をバランスよく伝えることが大切です。まず、冒頭でお祝いをいただいたことへの感謝をしっかり述べます。「先日は私たちの第一子誕生に際し、心温まるお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」といった形です。その後、赤ちゃんの名前や誕生日、性別などを軽く紹介すると、受け取る側に親しみやすさが増します。例えば「〇月〇日に〇〇(名前)が誕生し、おかげさまで元気に成長しております。」などです。さらに、いただいたお祝いがどのように役立っているかを添えると具体性が出ます。「いただいたベビー服は毎日大切に使わせていただいております。」といった一文は、贈り物への感謝をより実感させます。結びには「これからも家族共々よろしくお願いいたします」や「お会いできる日を楽しみにしております」といった前向きな言葉を入れます。形式としては、カードなら短くまとめ、手紙なら時候の挨拶を入れた上で、これらの要素を組み込みます。例文としては、「先日は心温まるお祝いをいただき、ありがとうございました。〇月〇日に無事長女〇〇が誕生し、すくすく育っております。いただいた品は大切に使わせていただきます。お会いできる日を楽しみにしております。」といった形が使いやすいです。
結婚内祝いで使える例文
結婚内祝いのメッセージでは、新生活の喜びと、お祝いをいただいた感謝を丁寧に伝えます。冒頭で「このたびは私たちの結婚に際し、心温まるお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」と感謝を述べます。その後、結婚式や新生活の様子を簡単に伝えると近況報告にもなります。「おかげさまで〇月〇日に無事挙式を終え、新居での生活も落ち着いてまいりました。」というような形です。いただいたお祝いがどのように役立っているかを具体的に書くのも効果的です。「いただいたキッチン用品は、毎日の食卓で大切に使わせていただいております。」などです。最後に、今後のお付き合いをお願いする一文を添えます。「これからも温かく見守っていただけますと幸いです。」などが適しています。例文としては、「このたびは心温まるお祝いをいただき、ありがとうございました。〇月〇日に無事挙式を終え、新生活も順調にスタートしております。いただいた品は大切に使わせていただきます。今後とも末永くよろしくお願いいたします。」といった形が無難かつ丁寧です。
新築内祝いで使える例文
新築内祝いでは、新居完成の喜びと、それを支えてくれた相手への感謝を込めます。まず感謝の言葉から始めます。「このたびは新居完成に際し、お心のこもったお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」と述べ、その後、新しい家での生活の様子を簡単に触れます。「おかげさまで快適な生活を始めることができ、家族一同感謝しております。」などです。さらに、いただいたお祝いの具体的な活用について触れると、感謝の気持ちがより伝わります。「いただいた観葉植物はリビングを明るく彩ってくれています。」などです。結びには、訪問の誘いや再会を願う言葉を入れると温かみが増します。「ぜひ新居にも遊びにいらしてください。」や「お会いできる日を楽しみにしております。」などです。例文としては、「このたびは新居完成に際し、温かいお祝いをありがとうございました。おかげさまで快適な生活を始められました。いただいた品は大切に使わせていただきます。ぜひお近くにお越しの際は新居にもお立ち寄りください。」という形が汎用的です。
快気内祝いで使える例文
快気内祝いは、回復の報告とお礼が中心になります。冒頭で「このたびは療養中に温かいお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。」と感謝を述べ、その後、病状が回復したことを簡潔に伝えます。「おかげさまで体調も回復し、日常生活に復帰しております。」などです。いただいたお見舞いへの感謝を具体的に述べると、より温かみが増します。「いただいたお見舞いの品は、療養中に大変励みになりました。」などです。結びには、再会を楽しみにする言葉や健康への感謝を加えます。「今後は健康に気を付け、元気に過ごしてまいります。お会いできる日を心待ちにしております。」などです。例文としては、「このたびは温かいお見舞いをありがとうございました。おかげさまで快復し、日常生活に戻ることができました。これからも健康に留意してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。」という形が安心感を与えます。
その他お礼全般に使える例文
特定の祝い事に限らず、お世話になった方へのお礼として使える内祝いメッセージもあります。冒頭で「このたびはお心のこもったお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」と感謝を述べ、続けてそのお祝いがどれだけ嬉しかったかを表現します。「温かいお気持ちに触れ、心より感謝しております。」などです。贈り物をどのように使っているか具体的に伝えると、感謝が実感として伝わります。「いただいた品は、家族みんなで大切に使わせていただいております。」といった形です。最後に「今後とも変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。」や「またお会いできる日を楽しみにしております。」といった前向きな言葉で結びます。例文としては、「このたびは温かいお祝いをありがとうございました。お心遣いに深く感謝いたします。いただいた品は大切に使わせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。」という形が汎用性が高くおすすめです。
相手別・心に響くメッセージ例文集
友人に送るカジュアルな例文
友人への内祝いメッセージは、堅苦しくなりすぎず、日常会話に近い柔らかい言葉遣いがポイントです。冒頭で「先日は素敵なお祝いをありがとう!」と、フランクかつ感謝をしっかり伝えます。その後、いただいたお祝いの使い道やエピソードを交えて近況を伝えると、より親しみが増します。例えば出産内祝いなら「いただいたスタイ、毎日大活躍してるよ!」、結婚内祝いなら「もらった食器で早速ホームパーティーしたよ!」といった具体的な話を盛り込むと相手も嬉しく感じます。最後に「また近いうちに会おうね」「今度は我が家にも遊びに来て!」など、これからの交流を楽しみにしている一文を加えます。例文としては、「先日は心のこもったお祝いをありがとう!〇〇(赤ちゃんの名前)もすくすく成長中で、いただいた服は早速お気に入りで着せています。落ち着いたらぜひ遊びに来てね!」といった形がおすすめです。友人だからこそ、感謝と共に距離感を感じさせる言葉を入れることが大切です。
会社の上司や取引先向けの例文
会社の上司や取引先へのメッセージは、ビジネス的な礼儀を保ちながらも、個人的な感謝をきちんと伝えることが重要です。冒頭は「このたびは私どもの慶事に際し、格別なお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。」と改まった表現を用います。その後、いただいたお祝いへの感謝と、それがどのように役立っているかを簡潔に述べます。「お贈りいただいた品は、新生活の中で大切に使わせていただいております。」などです。結びには「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。」といったビジネスでの関係を意識した言葉を加えます。例文としては、「このたびは結婚に際し、格別なお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。おかげさまで無事に挙式を終え、新生活も順調に始めております。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。」が無難で好印象です。
親戚・家族への例文
親戚や家族へのメッセージは、丁寧な言葉遣いの中にも親しみを感じさせる表現が望まれます。冒頭は「このたびは温かいお祝いをいただき、誠にありがとうございました。」とし、その後、近況報告を加えます。出産内祝いなら「おかげさまで母子ともに健康で、〇〇もすくすく成長しております。」、新築内祝いなら「新しい家での暮らしも落ち着き、毎日快適に過ごしております。」などです。また、訪問の予定や再会の希望を添えるとより温かみが増します。「ぜひ近いうちに新居にも遊びにいらしてください。」などです。例文としては、「このたびは心温まるお祝いをありがとうございました。おかげさまで元気に過ごしております。近々お会いできる日を楽しみにしております。」が使いやすいでしょう。
年配の方に向けた丁寧な例文
年配の方へのメッセージは、特に敬意を表す丁寧な言葉遣いを心がけます。冒頭で「このたびは私どもの慶事に際し、温かいお心遣いを賜り、心より御礼申し上げます。」と述べ、その後、体調や近況にも触れると安心感を与えられます。「おかげさまで体調も良く、日々穏やかに過ごしております。」などです。さらに、相手の健康を気遣う一文を添えると好印象です。「暑さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。」など、時候の挨拶を活用するとより丁寧になります。例文としては、「このたびは温かいお祝いを賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで新生活も順調に始まりました。暑さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。」が適切です。
英語で送るメッセージ例文
海外在住の知人や外国人の友人には、英語でのメッセージが喜ばれます。英語でも感謝の気持ちはシンプルに伝えることが大切です。例えば出産内祝いなら「Thank you very much for your warm gift to celebrate the birth of our baby. We are happy to share this joy with you.」といった形が適しています。結婚内祝いなら「We are deeply grateful for your generous gift and warm wishes on our wedding. We look forward to seeing you soon.」などが使いやすいです。短くても感謝・状況報告・再会の希望という3要素を入れるとバランスが良くなります。また、英語のメッセージでも最後に自分の名前を署名することを忘れないようにしましょう。
心を込めて書くためのメッセージ作成テクニック
相手に合わせた言葉選びのコツ
メッセージの言葉選びは、相手の年齢や立場、関係性に合わせることが最も重要です。例えば、目上の方や年配の方には「このたびはお心のこもったお祝いを賜り、誠にありがとうございました。」といった敬語を用い、丁寧な文章でまとめます。一方、親しい友人や同年代には「先日は素敵なお祝いをありがとう!」と、少しくだけた表現を使っても構いません。関係性に応じた言葉遣いは、相手に安心感を与えるだけでなく、距離感を適切に保つ役割も果たします。また、特定のエピソードや相手との思い出を盛り込むと、メッセージに個性が出て印象に残ります。例えば「大学時代からずっと支えてくれてありがとう。いただいた食器、大切に使うね。」などです。さらに、地域や文化による表現の違いにも注意しましょう。関西圏では「おおきに」、東北地方では「ありがとさま」など、方言をあえて使うことで親しみやすさを演出できる場合もあります。ただし、誤解を招く可能性がある言葉や、相手にとって意味がわかりにくい表現は避け、読み手に負担をかけないよう配慮することが大切です。
季節感を取り入れる工夫
季節の挨拶をメッセージに入れると、文章に温かみと彩りが加わります。日本には「時候の挨拶」という文化があり、季節に合わせた言葉を冒頭に添えるだけで、印象が格段に良くなります。例えば春なら「桜の便りが聞こえる季節となりました」、夏なら「暑さ厳しき折」、秋なら「実りの秋を迎え」、冬なら「寒さ厳しい日が続いておりますが」といった具合です。こうした挨拶は特に年配の方やフォーマルな相手に喜ばれます。また、季節感は文章の中だけでなく、カードや便箋のデザインにも取り入れられます。春には花柄、夏には涼しげな色合い、秋には紅葉モチーフ、冬には雪や星のイラストなどが映えます。さらに、季節の行事や旬の食べ物に触れると、より親近感が湧きます。「暑い日が続きますが、冷たいお茶で涼んでいただければ幸いです」など、贈り物との関連性を持たせると一層効果的です。
感謝の気持ちを強調する書き方
内祝いのメッセージでは、感謝の言葉が主役です。文章全体で「ありがとう」という気持ちをいかに強調するかが鍵となります。感謝を伝えるときは、一度だけでなく文章の中で繰り返し触れることで、気持ちの深さが相手に伝わります。例えば、「先日は素敵なお祝いをいただき、誠にありがとうございました。温かいお気持ちに触れ、心より感謝しております。」と、冒頭と中盤で感謝を述べると印象的です。また、感謝の対象を具体的に示すことも重要です。「いただいたタオルは肌触りが良く、毎日大切に使わせていただいております。」といった一文は、相手が選んでくれた品物に対する評価と感謝を同時に伝えられます。さらに、感謝の言葉の後に「これからもよろしくお願いします」や「またお会いできる日を楽しみにしています」といった未来志向の文章を添えると、前向きで温かい印象を残せます。
長すぎず短すぎない文量の目安
メッセージは長すぎると読み手に負担をかけ、短すぎると事務的な印象になります。カードの場合は50〜100文字程度、手紙の場合は200〜400文字程度が目安です。この範囲内で、感謝・近況報告・結びの3要素を盛り込むのが理想です。短い文章の場合は要点を簡潔にまとめ、長めの場合は具体的なエピソードを入れて膨らませます。例えば短いカードなら「先日は素敵なお祝いをありがとうございました。大切に使わせていただきます。」で十分です。長い手紙なら「先日は温かいお祝いをいただき、誠にありがとうございました。いただいた食器は、家族の食卓を華やかにしてくれています。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。」など、自然な流れで文字数を調整します。
失礼にならないためのNG表現
内祝いのメッセージでは、相手を不快にさせる可能性のある言葉や表現は避ける必要があります。例えば、金額や品物の価値を直接的に表す言葉はNGです。「高価な」「値段の張る」などは避けましょう。また、不幸や病気などを連想させる言葉も内祝いには不向きです。さらに、命令形や強い言い回しも避け、「ぜひ来てください」より「お時間が合いましたらお越しください」の方が柔らかい印象になります。相手との距離感を適切に保ちつつ、礼儀を欠かない文章が理想です。
まとめ
内祝いを郵送する場合、相手への感謝の気持ちが確実に届くよう、マナーや文章の工夫が欠かせません。まずは送るタイミングや熨斗・包装の選び方など、基本のマナーを押さえましょう。郵送は便利ですが、直接会って渡す場合と違い、表情や声で感謝を伝えることができません。そのため、必ずメッセージカードや手紙を添えて、心のこもった文章で感謝を表現することが大切です。また、相手との関係性や年齢、立場によって言葉遣いや文章の形式を使い分けることで、より心に響くメッセージになります。さらに、季節感や具体的なエピソードを盛り込み、文章に温かみを加えることもポイントです。最後に、失礼にあたる可能性のある言葉や表現は避け、相手が受け取って嬉しい気持ちになれる文章を心がけましょう。こうした細やかな配慮が、内祝いの価値を何倍にも高めてくれます。