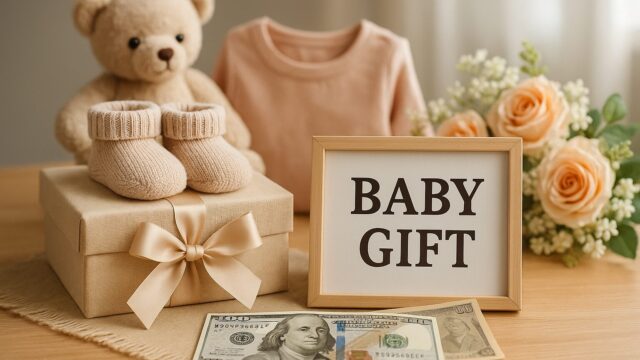赤ちゃんが生まれてから100日目に行われる「お食い初め」。
「一生食べ物に困らないように」と願いを込めるこの行事は、古くから日本に伝わる大切な伝統です。でも最近では、「やらない選択」をするご家庭も増えてきています。
「時間がない」「準備が大変」「形式にとらわれたくない」…そんな現代ならではの理由がある一方で、「意味を知るとちょっと後悔しそう」「何かだけでも残したい」という声も。
この記事では、「お食い初め」の本当の意味や願いを深掘りしつつ、やらないという選択肢についても前向きに考えられるよう、丁寧にご紹介していきます。大切なのは、親の気持ちと赤ちゃんへの愛情をどう形にするか。そんなヒントを、あなたにお届けします。
お食い初めって何?由来と本当の意味を知ろう
「お食い初め」の歴史と起源は平安時代?
お食い初め(おくいぞめ)は、赤ちゃんが生まれてから100日目ごろに行う伝統的な儀式で、「一生食べ物に困らないように」という願いを込めて、食事を用意し、食べさせる真似をする行事です。この習慣は実はとても古く、起源は平安時代にさかのぼるとされています。もともとは貴族階級の間で始まり、赤ちゃんが生まれて初めて「箸」を使う儀式として「箸初め(はしぞめ)」や「百日(ももか)祝い」と呼ばれていました。
当時は乳児死亡率が高く、赤ちゃんが無事に100日を迎えられることは家族にとって大きな喜びでした。そのため、100日目という節目をお祝いすることで、これからも元気に育ってほしいという祈りを込めていたのです。また、初めての固形物(といっても実際は食べさせる真似だけ)を与えるという行為には、「健やかに育ち、口から食事を取れるまでに成長した」という証でもありました。
江戸時代に入ると武家や庶民にも広がり、現在のような「祝い膳」や「歯固めの石」を使う風習が一般化していきます。こうして日本の家庭行事の一つとして定着していきました。
つまり、お食い初めはただのイベントではなく、長い歴史を持ち、日本人の「子どもの成長を願う心」がぎゅっと詰まった行事なのです。今ではやり方も自由になってきましたが、その背景にある深い意味を知ることで、やるかどうかを考えるヒントになりますね。
「一生食べ物に困らないように」の意味とは
お食い初めでよく聞くフレーズが「一生食べ物に困らないように」という願いです。これは単に「ご飯を食べていけるように」という意味にとどまらず、もっと広い意味が込められています。
まず、この言葉の根本には「健康に育つこと」「経済的に自立できること」「社会とのつながりの中で幸せに生きていけること」など、多くの親の願いが込められています。つまり、「食」に象徴されるのは「生活の安定」であり、「幸せな人生」そのものです。
昔は飢饉や病気などで子どもが育たないことも多く、「食べること」は生きることそのものでした。だからこそ、お食い初めは命の喜びを祝う儀式であり、「これから先も生きていく力をもってほしい」という深い願いが込められていたのです。
また、「食」に困らないということは、親が子どもに「将来、社会の中で困らずに暮らしてほしい」「自分の力で生きていけるようになってほしい」という願望でもあります。今の時代に置き換えれば、単にお金や食べ物に困らないというよりも、「自分の人生を豊かに生き抜く力を育んでほしい」という思いと考えると、さらに理解が深まりますね。
たとえ儀式を行わないとしても、この言葉の持つ意味を知るだけで、子どもの将来を想う気持ちが自然とあふれてくるかもしれません。
百日祝いとお食い初めの違い
百日祝いとお食い初めは、よく混同されがちですが、それぞれに意味と目的が少し異なります。
「百日祝い(ももかいわい)」は、赤ちゃんが生後100日を迎えたこと自体をお祝いする行事で、「無事にここまで成長したね」という意味合いが強いお祝いです。地域によっては90日や120日で行われることもあり、日数に多少の幅があります。これは赤ちゃんの成長速度や体調に合わせて柔軟に考えられてきたからです。
一方、「お食い初め」はこの百日祝いと同じ時期に行うことが多いですが、より「儀式性」が強いのが特徴です。食事の儀式として行われ、実際に赤ちゃんに食べさせる真似をするなどの決まった流れがあります。つまり、百日祝いが“成長のお祝い”であるのに対し、お食い初めは“成長を願う儀式”といえます。
この2つは同時に行われることも多く、「百日祝いの一環としてお食い初めをする」というケースが一般的です。ただし、儀式としてしっかりやるかどうかは家庭によって違い、最近では写真撮影だけで済ませる家庭や、祝い膳だけ用意して家族でお祝いするスタイルも増えています。
「やらない」という選択をするにしても、百日という節目に気持ちを込めて赤ちゃんの成長を喜ぶことが大切なのです。
地域によるしきたりの差は大きい?
お食い初めの風習は全国的に見られますが、地域によってそのしきたりや形式には違いがあります。
例えば、祝い膳に入れる料理の内容が異なるケースがよくあります。基本は「一汁三菜(ご飯・汁物・魚・煮物・香の物)」ですが、関西では「お赤飯」が主流なのに対し、関東では「白ご飯」を使うことも。さらに九州地方では、「雑煮」を加える地域もあり、それぞれの土地の食文化が反映されています。
また、「歯固め石」の使い方にも差があり、関東では「石を箸でちょんと触れさせ、赤ちゃんの歯茎に当てる真似をする」形式が多いですが、関西では「梅干し」や「タコ」を使う家庭もあります。中には「お食い初め自体をあまり重視しない」という文化を持つ地域もあるため、「やるのが当たり前」と感じない人もいます。
こうした地域差を知っておくと、「やらないこと」や「簡略化すること」に対して罪悪感を持たずに済むかもしれません。どれが正解ということはなく、大切なのは「子どもの成長を祝う気持ち」です。
もし自分の住んでいる地域に特有の風習があるなら、祖父母などに話を聞いてみると新しい発見があるかもしれませんね。
現代の家庭で見直されている背景とは
近年、「お食い初めをやらない」という選択をする家庭も増えています。これは決して伝統を軽視しているわけではなく、ライフスタイルや価値観の変化によるものです。
例えば共働き家庭では、平日に準備をする時間がない、土日に予定が詰まっていて日程を組めないなどの理由があります。さらに、家族が遠方に住んでいて集まれない、親世代との考え方にズレがある、といったケースも少なくありません。
また、SNSやネットの影響で「完璧なお食い初め写真」や「豪華な祝い膳」を目にすることが多く、「自分たちには無理かも」と感じてしまう人も。結果として、精神的な負担を避けるために「やらない選択」をする家庭が出てきているのです。
こうした背景には、「形式に縛られず、自分たちに合ったやり方で子どもを祝いたい」という、ポジティブな意識の変化も見て取れます。つまり、“やらない=祝っていない”ではなく、“自分たちなりの祝福の形を選んだ”ということなのです。
お食い初めに込められた5つの代表的な願い
健やかな成長と健康を願って
お食い初めに込められている願いの中でも、最も基本的で強いのが「健やかな成長」と「健康」の祈りです。生後100日という時期は、まだ体も小さく、免疫力も十分ではありません。だからこそ、昔から「これからも元気に育ってほしい」という親の切実な願いが込められてきました。
祝い膳の中には、「鯛」や「赤飯」など、おめでたい意味を持つ料理が多く並びますが、これもすべて健康と長寿を象徴する食材です。例えば鯛は「めでたい」にかけられており、赤飯は邪気を払うとされ、子どもの無病息災を願う意味があります。また、野菜の煮物や汁物には栄養のある具材が選ばれ、豊かな食生活を象徴しています。
現代では医療が進歩し、赤ちゃんの生存率も高くなっていますが、それでも育児の中で「風邪をひかないか」「よく寝ているか」「体重が増えているか」など、小さな不安はつきものです。だからこそ、この節目に「とにかく元気に育ってくれればいい」という素直な願いを形にすることは、親としても気持ちを整理する良い機会になります。
実際に食べさせるわけではなくても、赤ちゃんの口元に祝い膳を運ぶ仕草をしながら、成長してきた日々を振り返ることで、家族の絆もより深まるはずです。たとえ儀式として行わない場合でも、健康への感謝とこれからの願いを言葉にすることは、とても意味のあることだといえるでしょう。
食に困らない幸せを祈って
「一生食べ物に困らないように」という言葉は、お食い初めの最も有名なフレーズです。これは昔の日本で、食べ物が貴重であった時代背景を強く反映しています。飢饉や戦争、天災による食料不足が頻繁に起こっていた時代において、「食べ物があること=生きていけること」という直結した意味を持っていたのです。
そのため、赤ちゃんが100日を迎えたタイミングで「将来、食べることに困らない子になりますように」という祈りを込めて、初めての“食”に関する儀式が行われたのでしょう。この願いは現代にも通じる普遍的な思いです。どれだけ豊かな時代になったとはいえ、心も体も満たされる「食」のありがたさは変わりません。
「食べる力」は、単に栄養を取ることだけでなく、「生きる力」そのものでもあります。よく噛み、自分で食べ、楽しく食事をする――そういった習慣は、健康や集中力、心の安定にまで影響を与える大切な要素です。
また、最近はアレルギーや偏食の悩みを抱える家庭も多いため、「食に困らない」ことの意味は、より深くなっていると感じる人も多いのではないでしょうか。だからこそ、形式にこだわらなくても、「食に感謝する」「これからも楽しくごはんを食べてね」といった気持ちを込めるだけでも、お食い初めの本質は十分に果たされるのです。
人とのつながりを大切にしてほしいという願い
お食い初めは、家族が集まり赤ちゃんの成長を祝うイベントでもあります。この場には、父母だけでなく、祖父母や親戚、兄弟姉妹が顔をそろえることも多いでしょう。こうした集まりには、「人とのつながりの中で生きていく大切さを知ってほしい」というメッセージが込められています。
人は一人では生きていけません。赤ちゃんも、両親や家族、周囲の助けによって成長していきます。その原点として「この子は多くの人に愛されて育っている」という安心感を、行事を通して感じてもらいたい、という気持ちがあるのです。
また、「食べる」という行為自体も、元々は誰かと一緒に囲むことが前提でした。家族や友人と同じ時間を過ごし、同じ食事を味わい、会話をする――そういった中で心が育ちます。だからこそ、「一緒にご飯を食べることの大切さ」を、赤ちゃんにも将来的に理解してもらいたいという願いが、お食い初めには込められているのです。
お食い初めをやらないとしても、日常の中で「ごはんを囲む時間」を大切にしたり、「家族の思い出」を写真や動画で残したりすることでも、この願いをしっかり伝えることができます。形式にとらわれず、愛情をどう形に残すかが大切なのです。
賢さ・知恵のある子に育つように
「お食い初め=食に困らない」だけではなく、「賢い子に育ってほしい」という知性への願いも込められています。これは、祝い膳に添えられる「梅干し」や「昆布(よろこぶ)」などの縁起物にも象徴されており、「頭の良い子になってね」「知恵がつきますように」といった親の思いが表れています。
特に「歯固め石」には「丈夫な歯が生えるように」という意味の他に、「しっかりとした意志をもつ人になってほしい」「芯のある人間に育ってほしい」といった象徴的な意味も込められていると言われます。賢さとは、単なる学力だけでなく、人との関わりや、自分で考えて行動する力を含んだ「人間力」のようなものです。
現代の子育てでは、知識だけでなく「非認知能力」といった心の強さ、柔軟性、社会性なども重視されるようになっています。そうした力の基礎は、乳児期から少しずつ育まれるもの。お食い初めを通じて、「あなたの成長を見守っているよ」「どんな子に育つか楽しみだよ」とメッセージを送ることが、将来の心の支えになるかもしれません。
たとえ儀式を省略したとしても、誕生日や節目のたびに「どんなふうに育ってほしいか」を言葉にして伝える習慣があれば、知性や人間性を育てる立派な教育の一部になるのです。
家族の愛を受けて育ってほしいという気持ち
お食い初めは「家族の愛情を形にする日」ともいえます。祝い膳を用意したり、儀式を行ったり、写真を撮ったりするそのすべての行動には、「あなたが生まれてきてくれてうれしいよ」「これからも大切に育てていくよ」という無言のメッセージが込められています。
特に最近では、コロナ禍や核家族化により、家族の集まりが減った中で、こうした儀式の機会が「愛情を再確認する場」になることもあります。おじいちゃんおばあちゃんが遠方に住んでいて会えない場合でも、オンラインで参加したり、後から写真を共有したりすることで、「つながっている」と感じられる工夫も可能です。
また、赤ちゃん本人はまだ記憶には残りませんが、成長してから写真や動画を見たときに、「自分はこんなに愛されていたんだ」と知ることで、自己肯定感の基礎が育つことも期待できます。
形式ばらず、たとえお食い初めをやらなかったとしても、子どもの成長を願って何かひとつでも家族で行った思い出があれば、それは一生の宝物になります。要するに、「儀式をやるかどうか」ではなく、「どんな気持ちで向き合うか」がもっとも大切なのです。
「やらない選択」はアリ?増えている理由とは
忙しくて準備できないという現実
お食い初めは、赤ちゃんが生後100日を迎える大切な節目の儀式ですが、現代の家庭では「忙しくて準備できない」という現実的な理由から、やらない選択をする人も増えてきました。特に共働きの家庭では、育児と仕事の両立に追われる毎日で、細かな準備をする余裕がないというのが正直なところです。
お食い初めには、祝い膳の食材を用意したり、器を選んだり、手順を調べたりと、思った以上に多くの準備が必要です。さらに、家族が集まる時間の調整や、写真撮影の段取りも考えなければなりません。こうした準備の負担が大きく、「やりたいけどできなかった」という声は少なくありません。
また、赤ちゃん自身のコンディションも大きな要因です。生後3カ月の頃は、まだ昼夜のリズムも安定しておらず、体調を崩しやすい時期でもあります。泣いたり、ぐずったりすることも多いため、「せっかく準備しても落ち着いてできないかもしれない」という不安から、無理に行うことを避ける家庭もあります。
最近では、お食い初めの代行サービスや祝い膳の宅配なども増えていますが、それでも「そこまでする必要があるのかな」と感じる人もいるでしょう。そうした考え方も自然であり、誰かと比べる必要はありません。
大切なのは、「どうしても形式を整えなければならない」というプレッシャーに押しつぶされるのではなく、子どもの成長を自分たちのペースで祝ってあげること。やらなかったからといって、親の愛情が薄れるわけではありません。むしろ、日々の育児に奮闘していること自体が、何よりも大きな愛情の証なのです。
家族構成や環境の違いによる判断
お食い初めをやるかやらないかは、家族構成や生活環境によって大きく左右されるものです。昔のように三世代同居が当たり前の時代と違い、現代では核家族化が進み、祖父母と離れて暮らしている家庭も多くあります。そのため、儀式に必要な知識やサポートを得にくく、「どうやって進めればいいのか分からない」と不安になる親も少なくありません。
また、ひとり親家庭や外国に住んでいる家庭では、日本の伝統行事そのものが馴染みのないものになっていることもあります。さらに、再婚家庭やステップファミリーなど、多様な家族の形がある現代では、必ずしも全員が同じ行事に共感するとは限りません。
さらに、親世代との考え方の違いも一因です。例えば祖父母が「絶対やるべき」と考える一方で、親は「無理に形式を整える必要はない」と思っている場合、話し合いや調整に気を使うことになります。このようなストレスを避けるために、「今回はやらない」という決断を下す家庭もあるのです。
環境の違いは、それぞれの家庭の個性でもあります。お食い初めをするかどうかに正解はなく、自分たちの暮らし方に合った形で赤ちゃんの成長を祝えば、それで十分です。重要なのは、「どうしたら家族みんなが心地よく、温かい気持ちで過ごせるか」を考えること。その結果として「やらない選択」になるのであれば、それも立派な愛情表現なのです。
儀式にこだわらないというライフスタイル
最近では、「儀式や伝統にあまりこだわらない」という考え方の家庭も増えています。これは、いわゆる“ミニマルライフ”や“合理的な子育て”を大切にする人たちの間で広がっている傾向です。「意味のあることだけを取り入れる」「不要な負担を減らす」といった価値観が広まる中で、お食い初めのような伝統行事をあえて行わない選択も自然な流れといえるでしょう。
こうした家庭では、「形式的なイベントをやるより、日常を大切にしたい」という意識が強くあります。毎日一緒に過ごす時間、笑顔でご飯を食べる時間、肌を寄せて遊ぶ時間――それらの積み重ねこそが、子どもにとって最も大切な“愛情の証”だと考えるのです。
また、お金の使い方や時間の優先順位を明確にしている家庭では、「高価な祝い膳や衣装にお金をかけるくらいなら、将来の教育費に回したい」「休日は家族で自然の中で遊びたい」といった選択をすることもあります。
もちろん、伝統を否定するわけではなく、「自分たちらしい形で祝いたい」という柔軟なスタイルなのです。やらないことで罪悪感を持つのではなく、自分たちにとって本当に意味のあることに集中する。それはむしろ、子どものために真剣に考えた結果の“選択”であり、何よりも尊重されるべきものです。
SNSなどの情報過多でプレッシャーに感じる人も
インスタグラムやYouTube、ブログなどで見かける「映えるお食い初め」の写真や動画。かわいい赤ちゃんの服装、豪華な祝い膳、おしゃれな飾り付けに囲まれた華やかな光景に、「うちもこうしなきゃ」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか。
しかし、SNSにあふれるキラキラした投稿の裏には、たくさんの準備や時間、労力がかかっています。そしてそれが「理想」として広まることで、「できない自分はダメなのかな」と落ち込んでしまうママやパパも少なくありません。
情報があふれる現代では、何が正解なのか分からなくなることもあります。「やるべきこと」が増えすぎて、「楽しむこと」が見えなくなってしまっては本末転倒です。
本来、お食い初めは家族が幸せを感じるための行事。周囲と比べるものではありません。大事なのは、自分たちに合ったスタイルで行うこと、そして無理をしないことです。
SNSはあくまで「他の人の一例」であって、「自分たちに合った方法」ではありません。もしプレッシャーを感じるなら、あえて見ないという選択も一つの方法です。情報から距離を置いて、目の前の赤ちゃんとの時間をじっくり楽しむこと。それが本当の意味での“祝う”という行為なのかもしれません。
無理せず「わが家流」を選ぶ家庭の声
「やらない」という決断をする家庭の中には、「わが家流のスタイルで祝えばそれでいい」と考えている人も多くいます。たとえば、「豪華な膳は用意しないけれど、家族でおいしいご飯を食べて乾杯した」「簡単な手作りケーキでお祝いした」など、それぞれの家庭なりの工夫や温かさが感じられるエピソードがたくさんあります。
こうした声から見えてくるのは、「お祝いの形は一つじゃない」ということ。形式ばらず、プレッシャーに感じず、日々の延長として祝うことが、むしろ自然で、心に残るものになる場合もあります。
また、「今回は見送ったけれど、初節句や誕生日でしっかりお祝いする予定です」といった声もあり、「すべてを完璧にやらなくてもいい」と柔軟に考える姿勢が広がっています。重要なのは、イベントの数ではなく、「どれだけ心を込めて子どもと向き合うか」なのです。
お食い初めをやらなくても、「愛されて育った」という事実は変わりません。赤ちゃんにとって最も必要なのは、きちんと祝われることよりも、毎日の中で大切にされること。わが家なりの形で、しっかりと愛情を伝えることができれば、それが一番の“正解”といえるでしょう。
やらないとどうなる?後悔しないための考え方
後から「やればよかった」と思う人の声
お食い初めをやらなかった人の中には、「やっぱりやっておけばよかった…」と後から後悔するケースも少なくありません。赤ちゃんの成長は一瞬一瞬が貴重で、その時にしかできない体験があるからこそ、「何か形に残しておけばよかった」という思いが時間が経つにつれて湧いてくるのです。
たとえば、子どもが大きくなってアルバムを見返すときに「どうしてお食い初めの写真がないの?」と聞かれたり、他の家庭の思い出話を聞いたときに「あのとき何かやっていれば…」と感じたりすることがあります。そうした声を見聞きすることで、「無理をしてでも少しだけでもやればよかったのかもしれない」と思う人もいます。
ただし、後悔の原因は「やらなかったこと」そのものではなく、「記念に残るものが何もなかったこと」にある場合が多いです。形式にこだわらず、写真1枚やちょっとしたメッセージでも、思い出として残っていれば、その気持ちは和らぎます。
また、「やらなかった」としても、それはその時の家庭の状況や選択によるものであり、後悔を恐れる必要はありません。むしろ、振り返ったときに「大変だったけど、精一杯育児していたな」と思えることの方がずっと大切です。後悔しないためには、「自分たちにできる範囲で、少しでも気持ちを形にしておく」ことがポイントになります。
写真や記録を残すだけでもOK
お食い初めの儀式をきっちり行わなくても、記念に写真や記録を残すだけでも十分意味があります。赤ちゃんの100日記念として、家族写真を撮ったり、成長の様子を書き留めたりすることで、「この日を大切に思っていたよ」という気持ちを未来に残すことができます。
実際、多くの家庭ではお食い初めの代わりに「100日記念フォト」を撮影しています。自宅で手軽にスマホで撮るだけでもよいですし、フォトスタジオに行ってプロにお願いする家庭もあります。着物やドレス、かわいい衣装を用意すれば、思い出に残る1枚が完成します。
また、アルバムや育児日記、デジタルフォトブックなどに、その日の出来事や思いを書き添えると、後で見返したときの感動が一層深まります。特に日々の育児に追われる中では、ちょっとした記録が未来の宝物になるのです。
重要なのは、形式的な儀式をするかどうかではなく、「どう思っていたか」「どんな気持ちで育てていたか」を残しておくこと。将来、子どもが成長したときにそれを見て、「自分は愛されていたんだ」と感じることができれば、それが最も価値のある記録になるはずです。
だからこそ、「やらない」選択をしたとしても、記念の写真1枚やメッセージひとつでも十分。その心がけだけで、お食い初めの意味をしっかりと受け継いでいると言えるでしょう。
意味だけ伝えても十分な家庭教育
お食い初めの本質は、「行事をこなすこと」ではなく、「その意味を理解し、子どもに思いを込めること」にあります。つまり、儀式をしなくても、お食い初めの背景や込められた願いを言葉で伝えるだけで、立派な家庭教育になるのです。
例えば「昔から100日目にお祝いする風習があってね」「一生食べ物に困らないようにって願う行事なんだよ」といった会話を、成長した子どもに伝えることは、文化や家族の歴史を知る大切なきっかけになります。知識としてだけでなく、「家族のあたたかい気持ち」を伝えることができます。
こうした会話の積み重ねは、子どもが成長するにつれて「自分は大切にされてきたんだ」と実感する要素になります。形式に頼らず、心の中に「家族の文化」を残すことができるのです。
また、こういった話を通じて、子どもに「感謝の気持ち」や「他人を思いやる心」が育つこともあります。「自分のために祈ってくれた家族がいた」と知ることが、他人を大切にする気持ちにもつながっていくのです。
大切なのは、伝える“形”より“中身”。儀式をするかどうかではなく、「子どもにどんな気持ちを伝えたいのか」を意識することが、親としての大きな役割になります。
「形」よりも「気持ち」が大事な理由
お食い初めに限らず、人生の節目には様々な行事があります。しかし、その一つひとつに共通して言えるのは、「形」よりも「気持ち」が大事だということです。どれだけ立派な料理や豪華な演出をしても、そこに「子どもを想う気持ち」がなければ、ただのイベントに過ぎません。
逆に、何の準備もできなかったとしても、「今日は100日だね」「元気に育ってくれてありがとう」と一言でも伝えられたなら、それはもう立派なお祝いなのです。その言葉の中には、親の想いと愛情が詰まっており、それこそが子どもにとっての最高のプレゼントになります。
また、子育ては日常の連続です。毎日の中にこそ、愛情を伝える機会がたくさんあります。夜中の授乳や寝かしつけ、離乳食の準備など、どれもが愛情そのもの。お食い初めという行事は、その“日常の育児”に気づきを与えるひとつのチャンスでもあります。
だからこそ、「やらない」ことをネガティブに捉える必要はありません。「気持ちがこもっていればそれでいい」と自信をもっていいのです。形にこだわらず、家族の気持ちがしっかり伝わっていれば、それこそが何より大切な“お祝い”なのです。
思い出の残し方は人それぞれ
お食い初めをやる・やらないに関わらず、大切なのは「どう思い出を残すか」ということです。そしてその方法は、家族によってまったく違っていいのです。誰かの真似をする必要もなく、自分たちらしい形で、記憶に残る工夫をしていくことがポイントになります。
たとえば、お祝いの言葉を手紙にして残しておく、写真にメッセージを書き込む、赤ちゃんの手形や足形をとって記念にする――そんなささやかな工夫でも、将来の大切な思い出になります。デジタルフォトアルバムや、動画に思いを込めて編集するのも最近では人気の方法です。
また、特別な食事を用意しなくても、家族で一緒に「ありがとう」と言い合える時間を作るだけで、その日が特別な記念日になります。「今日はパパとママが君を初めてお祝いした日だったんだよ」と、将来子どもに話してあげられるだけでも、それは素敵な記憶です。
思い出は、“形にする”よりも、“心に残す”ことが大切です。誰に見せるためでもなく、自分たちのために残すもの。だからこそ、自分たちらしく、無理なく、楽しんでできることを選べばよいのです。
やらない派のためのシンプル&代替アイデア集
お食い初め膳を簡易的に用意する方法
お食い初めを正式にやるのはハードルが高いけど、「少しは形にしたいな」と思う方には、簡易的な祝い膳を用意するという方法がおすすめです。必ずしも正式な一汁三菜をそろえる必要はなく、「わが家流」で気軽に用意できる内容にしても大丈夫です。
たとえば、スーパーで手に入る食材で以下のようなメニューが揃えられます。
| 料理 | 簡易アイデア |
|---|---|
| ご飯(赤飯or白米) | コンビニの赤飯おにぎりやレトルト赤飯でもOK |
| 焼き魚(鯛など) | 切り身の塩鮭やサバの味噌煮を代用しても◎ |
| 煮物 | 冷凍の和惣菜やレトルト煮物パックでも十分 |
| 香の物 | きゅうりの浅漬けやしば漬けなど手軽な漬物 |
| お吸い物 | インスタントのすまし汁で手間いらず |
これをワンプレートや小さなお盆に盛り付ければ、それだけで立派な「お食い初め膳」になります。かわいいランチョンマットや100均の和柄小皿などを使えば、雰囲気もグッとアップしますよ。
赤ちゃんには実際に食べさせる必要はありませんので、お箸で少しずつ口元に運ぶ仕草だけすればOKです。気軽な気持ちでやれば、思い出として十分価値あるものになりますし、後から写真を見返しても温かい気持ちになれるでしょう。
「ちゃんとやらなきゃ」と気負わずに、「できる範囲でやってみよう」という気持ちが何よりも大切です。忙しい日々の中でも、ちょっとした工夫で愛情を形にすることは十分可能です。
写真だけ記念に撮る「フォトお食い初め」
儀式は難しくても、写真だけを記念に撮る「フォトお食い初め」は、多くの家庭で選ばれているシンプルで効果的な代替案です。特にSNSやスマホで簡単に写真が撮れる今、わざわざ式を行わずとも、記念の一枚を残すだけで、気持ちをしっかり形にすることができます。
撮影方法はとても自由で、特別な背景や衣装を用意しなくても、赤ちゃんを抱っこして笑顔の写真を撮るだけで十分です。「100日記念」のカードや手書きのボードを添えれば、さらに気持ちが伝わります。ベビー服も普段着でOKですが、ちょっとしたスタイやお祝いカラーの洋服を選ぶと写真映えします。
フォトスタジオでの撮影も人気ですが、最近は自宅に出張してくれるカメラマンや、オンラインで編集できるフォトアルバム作成サービスも充実しています。コストを抑えつつ、プロのような仕上がりにできるのが嬉しいポイントです。
写真を撮るだけでも、「この日を大切にしたい」「成長を喜びたい」という気持ちがしっかりと伝わります。そして何より、将来子どもがその写真を見たとき、「こんなに祝ってくれたんだ」と実感できるのは、何にも代えがたい思い出になるでしょう。
忙しい毎日でも、写真1枚なら無理なく残せます。フォトお食い初めは、「やらない派」でも愛情をしっかり形に残せる、最高にシンプルで効果的な方法なのです。
家族だけの小さな乾杯や食事会でもOK
お食い初めのような儀式的なものが苦手だったり、準備が難しいという家庭には、もっとカジュアルに「家族だけの小さな乾杯」や「普段よりちょっと特別な食事会」をする方法もおすすめです。
例えば、「今日は100日記念だね」と言いながら、夕食時に家族でジュースやノンアルコール飲料で乾杯するだけでも、それは十分立派な「祝い」の形になります。食事も、いつものメニューに赤ちゃんの名前入りの旗を立てるだけ、ちょっと豪華なデザートを用意するだけでも、特別感がぐっと増します。
また、赤ちゃんにはまだ食事の内容が分からなくても、家族みんなが笑顔で過ごす時間が、その場の雰囲気や空気感として記憶に残ります。そしてそれは、写真や動画に残しておけば、将来必ず素敵な思い出になります。
こうした「ゆるいお祝い」の良さは、無理なく続けられることにあります。今後の初節句や誕生日などの行事も、「完璧にやらなきゃ」というプレッシャーがなくなるため、育児全体が少し楽になります。
大事なのは、「家族みんながその日を特別な日として認識していること」。たとえ10分でも20分でも、心を込めたひとときを過ごせれば、それが最高の記念になるのです。
メッセージカードで思いを残すアイデア
お食い初めのような行事を行わなくても、親としての想いを“言葉”にして残すのは、とても意味のあることです。その中でもおすすめなのが、赤ちゃんへの「メッセージカード」を書くというシンプルな方法。これはお金も手間もかからず、気持ちをしっかり伝えることができる素敵な記念になります。
書き方にルールはありません。「生まれてきてくれてありがとう」「100日間、元気に育ってくれて嬉しいよ」といった素直な気持ちを、一枚のカードに書くだけでOKです。日付を書いておけば、「このときこんなふうに思っていたんだな」と後から見返すこともできます。
もし将来的に育児アルバムやスクラップブックを作る予定があれば、その一部としてメッセージカードを貼るのもおすすめです。デジタルでも構いません。スマホのメモアプリや、LINEの自分宛てメッセージに残しておくのでも、立派な記録になります。
言葉にすることは、気持ちを整理し、記憶を形に残す手段でもあります。赤ちゃんが大きくなったときに読んで、「愛されていたこと」を知るきっかけになれば、それだけで十分に意味のある行動と言えるでしょう。
形式ではなく、心を込めた言葉こそが、もっとも大切な“お祝い”になるのです。
将来の子どもへの伝え方・話し方の工夫
お食い初めをやらなかった家庭でも、将来子どもにその理由や意味を伝えることで、大切な文化や愛情をしっかりと受け継ぐことができます。ポイントは、「やらなかった理由」ではなく、「どんな気持ちで子どもを見守っていたか」を伝えることです。
例えば、「当時はとても忙しかったけど、君のことをいつも思っていたよ」「100日目の夜は家族でごはんを食べて、元気に育ってくれてうれしかったんだよ」といったエピソードを、自然な会話の中で話してあげるとよいでしょう。
また、「お食い初めっていう行事があるんだよ」「一生食べ物に困らないようにっていう願いを込めるんだよ」と教えることも、文化や家族の歴史を知る大切な一歩になります。学校の授業では学べない、親から子への“心の教育”になるのです。
言葉にして伝えることは、子どもとの信頼関係にもつながります。過去の出来事を素直に話すことで、子どもは「大切にされている」「ちゃんと向き合ってくれている」と感じられるようになります。
大切なのは、「やっていないこと」に引け目を感じるのではなく、「今からでも伝えられることがある」と前向きに考えることです。言葉には、過去を未来につなげる力があります。
その力を、親としての愛情とともに、子どもに届けてあげてください。
まとめ
お食い初めは、赤ちゃんの生後100日を祝う大切な節目の行事であり、「一生食べ物に困らないように」という願いを込めた日本の伝統文化です。その意味は、単に食事の儀式にとどまらず、「健康」「幸せ」「つながり」「知恵」「愛情」といった、さまざまな親の願いが詰まっています。
しかし、現代の家庭においては、ライフスタイルや家族構成の多様化、仕事や育児の忙しさ、価値観の違いなどにより、「やらない」という選択をする人も増えています。それは決して間違いではなく、「無理せず、わが家らしく」という新しいスタイルの一つとして、自然な選択肢になってきているのです。
大切なのは、形式にとらわれることではなく、「子どもの成長を心から喜び、愛情を注ぐこと」。それが写真であっても、手紙であっても、家族の乾杯でも、どんな形でも構いません。親としての想いを、どのように子どもに伝え、残していくかが本質です。
「やらない」と決めた方も、「形を変えてみようかな」と迷っている方も、このブログ記事が自分たちなりの“お祝いの形”を見つけるきっかけとなれば幸いです。